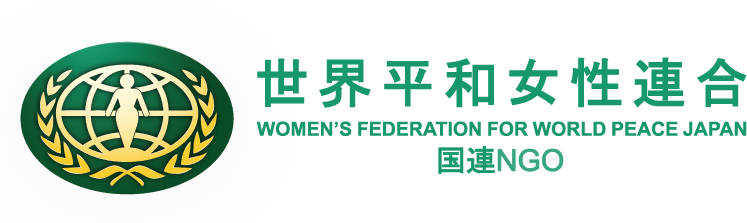ソロモン諸島
Solomon Islands
ソロモン諸島は南太平洋に浮かぶ約1000もの島から成り立つ島国です。肥沃な熱帯雨林や海に覆われた国土には植物、鳥類、蝶の種類が多く、魚介類も豊富です。
1998年から2003年の5年間にわたって民族紛争(エスニック・テンション)が続き、国家崩壊の危機を経験しました。
ソロモン諸島では義務教育制度がないため、中等教育からは辞めていく生徒もいます。小学校6年、中等部3年、高等部2年、3年次に進級試験を受け、合格者のみ上の学年へ進級できる仕組みとなっています。
ソロモン諸島での活動
【読書推進活動/ソロモンの子供たちに読書の楽しみを】

2024年より、読書推進に特化したプロジェクトを開始しました。
ソロモン諸島では書店や製紙工場がなく、本を読む習慣や文化が根付いていません。学校の先生方でも、聖書や教科書は読むものの、それ以外の本を読んだことがない人が多くいます。
国内にある書店はキリスト教書店1店舗のみ。近年になってようやく、市内の雑貨店2、3軒で数種類の絵本を扱うようになりました。
市の図書館もありますが、本棚には半分ほどの汚れた本しかなく、利用者の姿はほとんど見られませんでした。
過去30年間にわたり、市内の学校へ本の寄贈を続けてきました。しかし、子どもたちは最初こそ挿絵に興味を示すものの、読書習慣には結びつきませんでした。
読書習慣が根付かない背景には、以下のような要因があります。
• 英語を読むことに慣れていない(日常の使用言語はピジン英語)
• 本にどのようなことが書かれているか想像できない
• 「本=面白い」という体験がない
そこで、まずは本好きな子ども「本の虫」を育てることを目標に、幼児への読み聞かせを続けてきました。
ニューホープをモデルケースとし、幼稚園児への読み聞かせを定着させるため、先生方への啓蒙活動を行いました。
絵本はオーストラリアWFWPの協力を得て、美しく道徳的な良書のみを1冊ずつ選び、寄贈してもらっています。その結果、毎日の読み聞かせが定着し、本に関心を持つ子どもが増え、読み書きが得意な子が多くなりました。
この成功例をもとに、今後は市内の幼稚園や学校での読み聞かせ推進活動へと拡大し、読書文化の定着を目指します。
このプロジェクトを通じて、子どもたちが多くの良書と出会い、想像力や思考力、道徳心、創造性を育み、人生の指針となる本と巡り合えるよう努めていきます。

「ニューホープアカデミー教育支援」について
「ニューホープアカデミー教育支援」は、学校がソロモン教育省への登録校となり、国からの補助金を得て独立運営が可能となりました。そのため、2022年をもって日本WFWPからの支援は終了しました。
ソロモン諸島基礎情報
国名/首都
ソロモン諸島/ホニアラ
基本情報
| 人口 | 65万人(2018年、世界銀行) |
| 国土面積 | 28,900 km²(岩手県の約2倍) |
| 言語 | 英語の他、ピジン英語 |
| 宗教 | キリスト教(95%以上) |
※出典:外務省ウェブサイト
統計情報
| 平均寿命 |
| 73歳*¹ |
| 乳児死亡率(1歳未満) |
| 17人/1,000人*² |
| 幼児死亡率(5歳未満) |
| 20人/1,000人*² |
| 一人当たりの名目GDP |
| 2,370USドル*¹ |
| 消費者物価上昇率 |
| 1.6%*¹ |
| 初等教育修了率 |
| 男子: 84% 女子: 90%*² |
| 若者(15-24歳)の識字率 |
| 男子: -% 女子: -%*² |